東京・神奈川入試2日目ですね。
2/1の午前校・午後校の合格発表がされ始めていますが、国立などまだこれからなので、受験生や親御さんはコロナに気をつけて本番を迎えられるよう応援しています。
今回は前回に引き続き、中学入試で問われる力を紐解いて解いて解説します。

1.社会
-
-
社会の単元自体は小学校の学習範囲でも、求められる知識の広さや深さは、一部の単元を除き、「中学校の教科書の内容をほぼ網羅するレベル」に達します
-
-
-
例えば、小学校では、「ある地域でのりんごの収穫量が多い」と覚えれば良かったのが、中学入試では、「りんごの収穫量が多いのは他にどんな地域があり、それらの地域に共通する気候の特徴は何か?」という多面的な思考力が求められる
-
-
-
社会の広範な範囲に対応するためには、「1つの知識に関連する内容を結びつけて学び、定着させる!」ことがカギとなります

色々な知識や情報を結びつける訓練が必要
-
-
-
また今年、灘でも話題になった問題、「『GAFA』のGにあたる企業名は?」は、そもそも知らないと回答できない問題なので、現象の紐付けの訓練だけではなく、時事問題への対応も必要
-
-
-
息子も読んでいる「読売KODOMO新聞」。月額550円(税込)でリーズナブル&週イチ配達で読みやすく時事問題の対策に役立つ!
-
2.理科
-
-
理科は小学校と学習する単元が被っているように見えて、実は大きく異なるのは、求められる知識の細かさ
-
-
-
小学校では、昆虫の体が頭部・胸部・腹部で構成されているだけの理解で良かったが、中学入試では、羽の形状から足の生え方まで、人に説明できるレベルの詳しい理解が必要
-
-
-
次に重要なポイントが思考力。実験結果のグラフなどの内容を整理して、結論を導く過程を自分自身で考えられるか。難関校ほど、思考力を問われる問題が多くなります
-

「なぜ?どうして?」物事の本質的な理解と思考力が求められる
今回はここまで!
最後までお読み頂きありがとうございました!
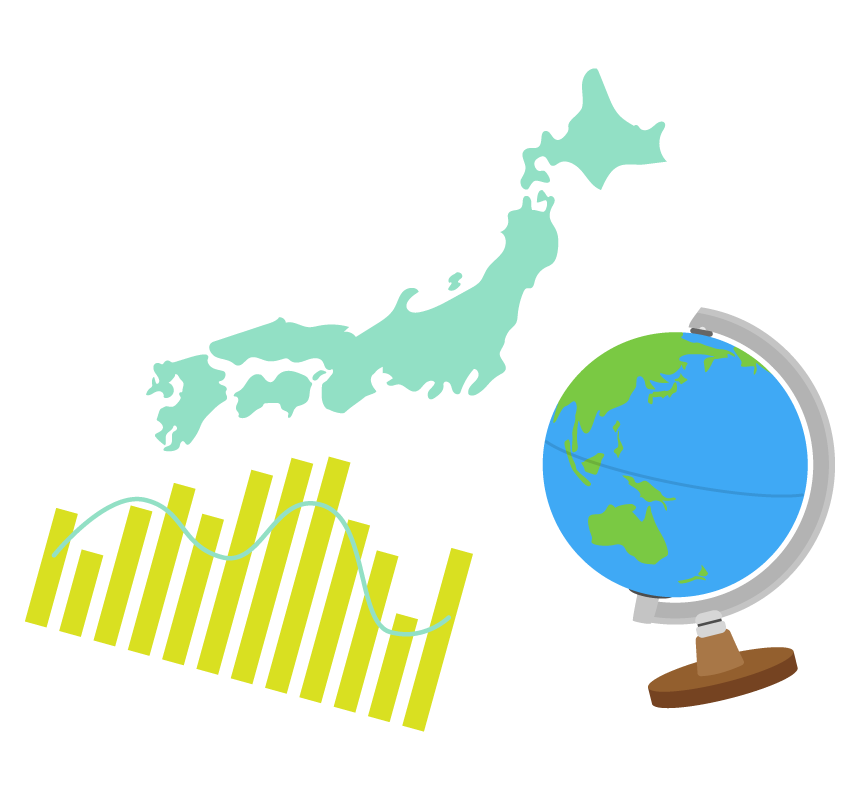
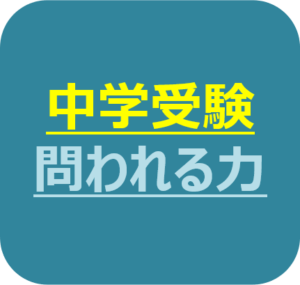








コメント